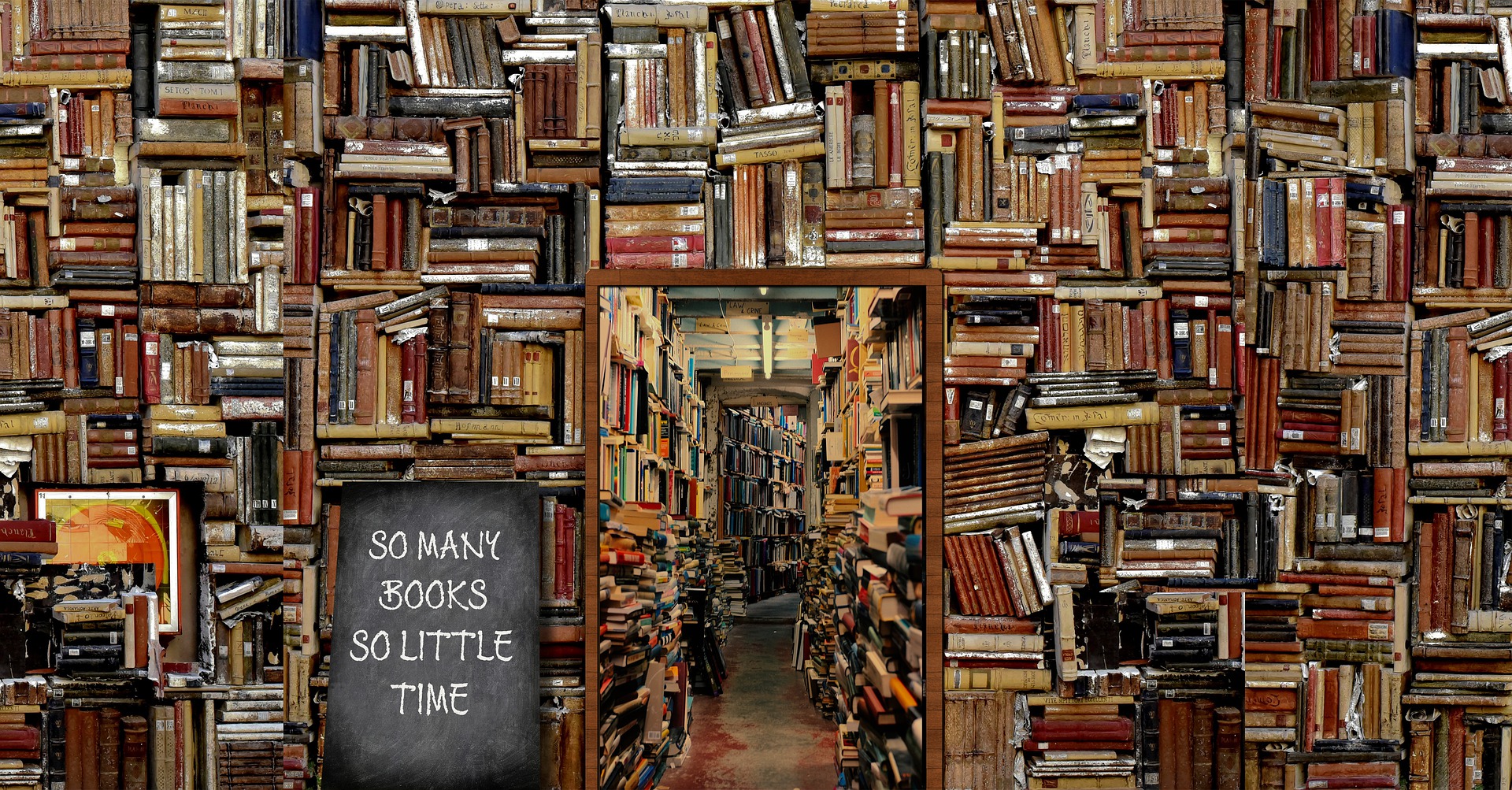
用語集
◆お酒の適量とは
説明
適度な飲酒によって、健康促進を行うことができるお酒の量を解説。
治療効果
アルコールによる健康効果
- リラックス効果
- 一時的な血行促進
- 適量であれば寿命が伸びるというデータあり
ビールの健康効果
日本酒の健康効果
- アスパラギン酸→疲労回復
- アラニン→免疫強化
- アルギニン→成長ホルモンの分泌促進
- グリシン→睡眠改善
- グルタミン酸→脳の活性化
- システイン→肌トラブル改善
- スレオニン→肝機能の強化
- チロシン→ストレス耐性の強化
- フェニルアラニン→記憶能力の強化・リラックス効果
- リジン→疲労回復・カルシウムの吸収促進
- ロイシン→筋肉・肝機能の強化
焼酎の健康効果
- 血栓を溶かし血液をサラサラにする
- 善玉コレステロールを増やす
ワインの健康効果
- ファイトケミカルの一つであるポリフェノールによる強い抗酸化作用でアンチエイジングや動脈硬化、認知症、がん予防に効果が期待できる。
- アントシアニンが含まれており、眼精疲労などに効果がある。
蒸留酒の健康効果
- 糖質やプリン体が一切含まれていない
治療方法
アルコール飲料は適量を超えると、健康効果よりもアルコールによる健康被害を受けることとなる。そのため、飲酒量はしっかり適量を見極める必要がある。アルコール飲料の適量を考える際に基準とするのは純アルコール度数である。
純アルコール度数が7〜40gが適量と言われている。純アルコール度数が60gを超えると飲み過ぎであると判断される。アルコールに対する耐性は個人差があるため、平均で20gほどで飲酒をしてみて、体調不良などの症状が現れれば飲酒量を減らすように調整するべきである。
純アルコール度数の求め方は「お酒の度数(%)✖︎お酒の量(ml)✖︎0.8➗100」で求めることができる。具体的な適量の指標としては「ビール中ジョッキ2杯」「日本酒2合」「サワー(7%)2杯」程度である。

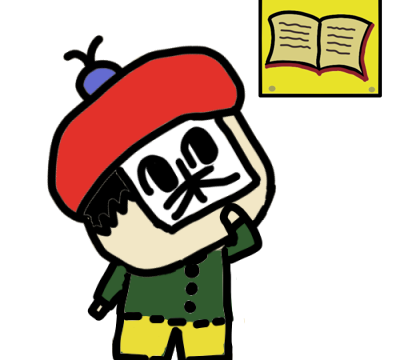
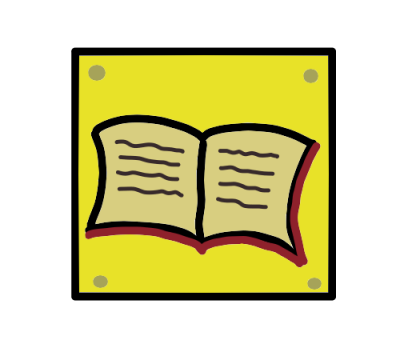




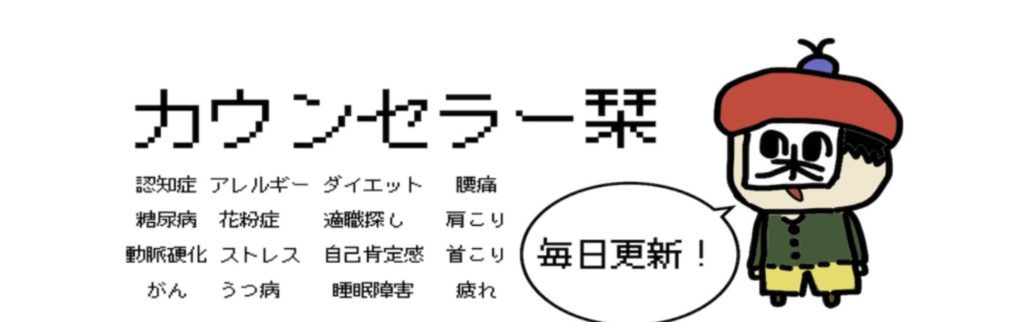
コメント